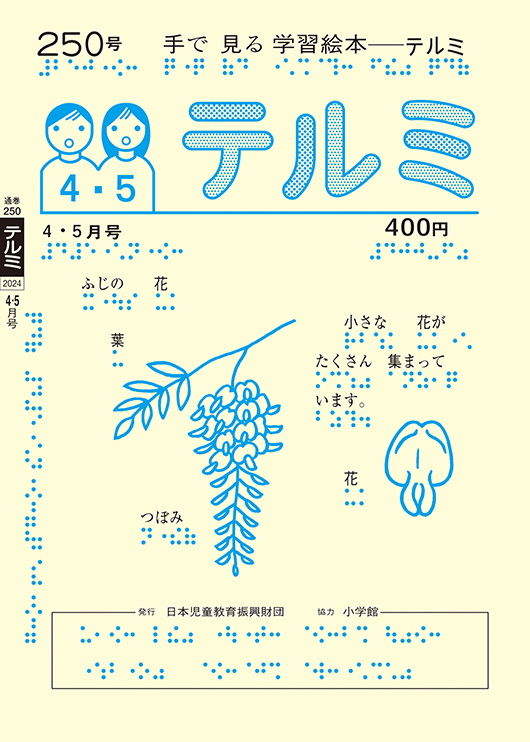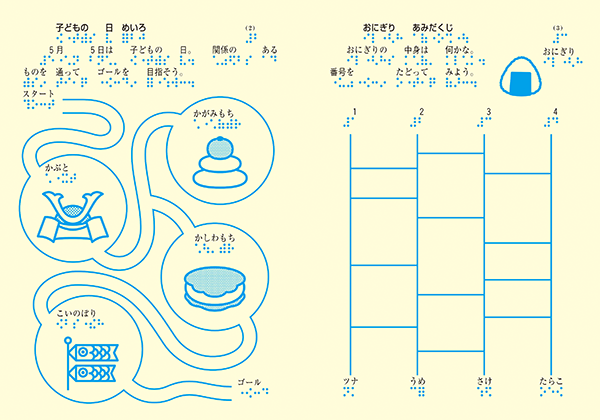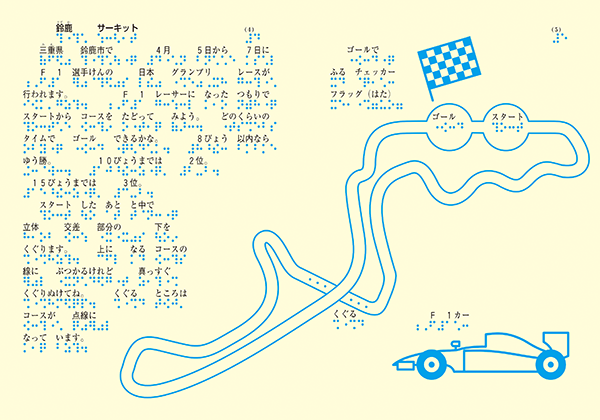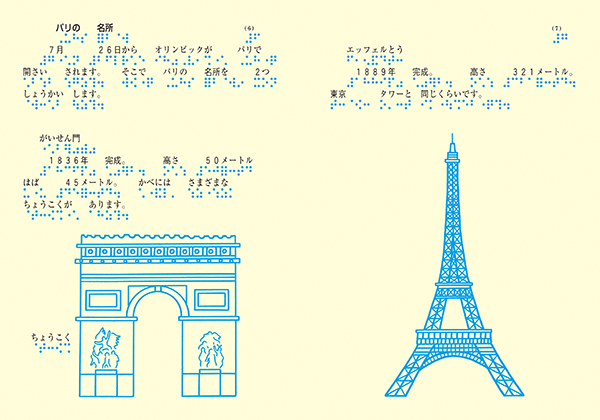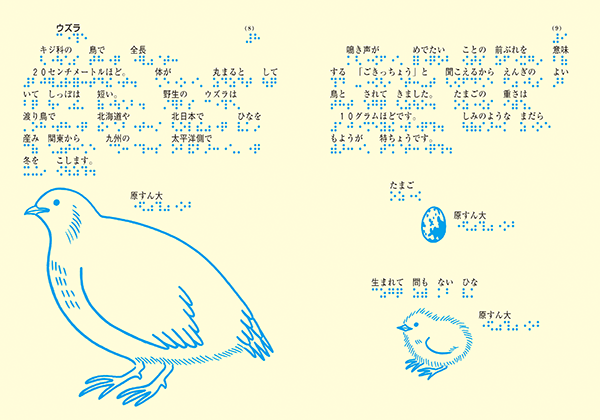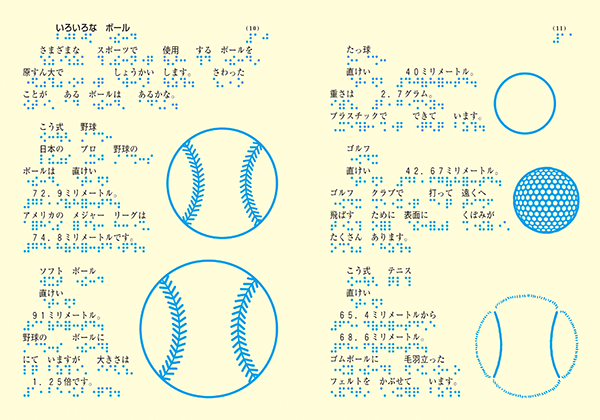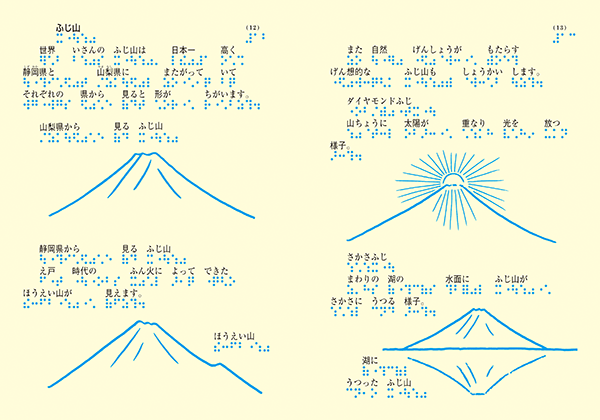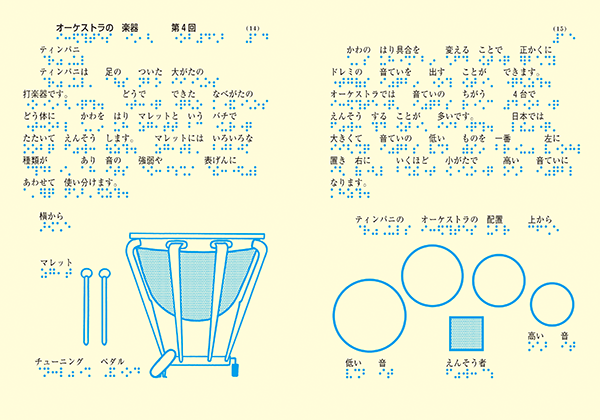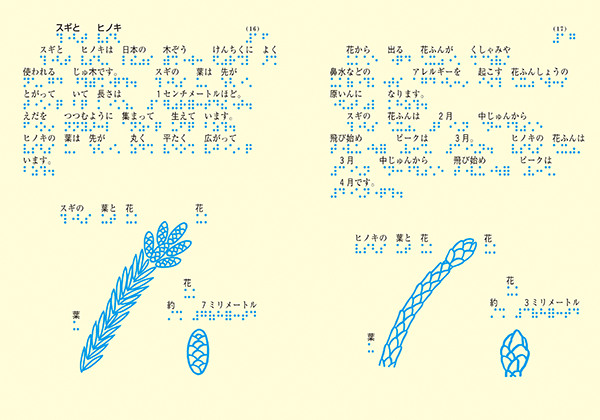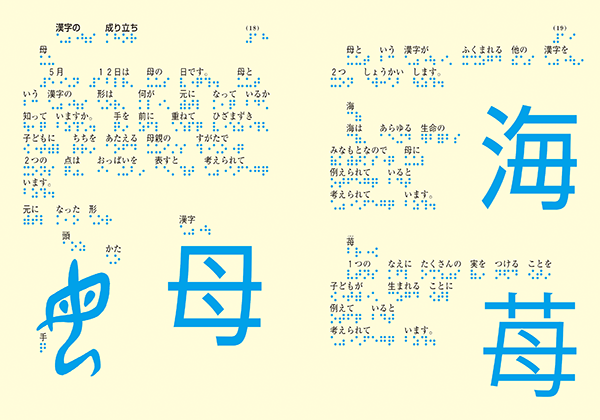ここからメニューがあります
ここから本文
最新号の内容
表紙
クリスマスリース
クリスマスが近づくと、家のドアなどに飾るクリスマスリース。材料にはヒイラギやモミなどの1年を通して葉をつける常緑樹の葉がよく使われ、リボンや小さなリンゴなどを飾ったりします。魔除けや、幸福を願う意味が込められているといわれています。
2ページから3ページ
東京タワー
1958年12月23日に完成したことから、12月23日は「東京タワーの日」ともされています。てっぺんのアンテナは2011年の東日本大震災の影響で曲がってしまいましたが、翌年に修復されました。600段の外階段を登ると、東京タワーのマスコットキャラクターノッポン公認の「のぼり階段認定証」がもらえます。
4ページから5ページ
グリーンランドとオーロラ
グリーンランドは独立した国ではなくデンマーク王国の一部で、人が住んでいるのは海岸沿いのみです。世界最大の島で、大部分が北極圏に属しています。グリーンランドの極夜は11月下旬から1月の初めが最も暗いといわれていて、クリスマスからお正月の時期はほぼ暗闇ですが、オーロラはこの時期によく見られるそうです。
6ページから7ページ
アンモナイト
アンモナイトの殻の内部には空気の部屋がいくつもあり、その空気の圧力を調節して浮き沈みしていたようです。同じアンモナイトでも自由に泳ぎ回るもの、植物にくっつき完全に海底で生活するものなど、いろいろな種類がいました。白亜紀と呼ばれる時代が終わる約6600万年前に、恐竜と共にアンモナイトも絶滅したといわれています。
8ページから9ページ
新井薬し
正式名は「新井山梅照院薬王寺」といいます。かつて徳川二代将軍の娘が目の病にかかった時にお祈りをしたところ、たちまち完治したという言い伝えから目の病にご利益があるとされています。点字のおみくじは2025年から始まりました。ふりおみくじは逆さまにした時に棒が下に落ちないようにプラスチックのケースに入っています。
10ページから11ページ
馬と人の関わり
十二支それぞれの動物に幸せを願う意味が込められていて、古くから農耕などで活躍してきた馬は「豊作」や「健康」といった意味があります。日本の在来馬 は今回紹介した宮崎県の御崎馬を含め、北海道の道産子 、長野県の木曽馬、愛媛県の野間馬、長崎県の対州馬 、鹿児島県のトカラ馬、沖縄県の宮古馬と与那国馬の8種類います。
12ページから13ページ
作って食べよう クルミクッキー
クルミクッキーのレシピです。オーブントースターを使う際は熱くなるので気をつけてください。機種によって焼き時間が違うので、調整しながら作ってみてね。
14ページから15ページ
かげのでき方
懐中電灯などの照明を使った影のでき方を説明しています。光は必ず真っすぐ進み、その光が物などに当たると後ろ側には光が届かない部分ができ、そこが影となります。高い位置から光を当てると影は短く、低い位置から当てると長くなります。
16ページから17ページ
かげのでき方とおせちあみだくじ
16ページの「かげのでき方」は光をえんぴつに当てた時にできるかげの長さの違いについて説明しています。「おせちあみだくじは」好きなおせちを選んで、自分の将来や性格をうらないます。
18ページから19ページ
正月遊びめいろ
昔ながらの正月遊びである羽子板、かるた、コマ、凧あげをたどりながらゴールを目指します。この中のどれかで、遊んだことはありますか。
20ページ
クイズ 冬じ
冬じに食べると風邪をひかないといわれている野菜は何か? 3つの中から正解を1つ選びます。ホームページからの入力、またはハガキに答えを書いて1月13日までに送ると正解者の中から抽選で10名様にテルミ特製の図書カードが当たります。
本文ここまで